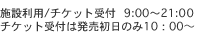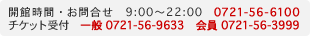|
 |
| この作品に関しては今更なにも語ることが無いほどにオペラファンならずともよく知られた作品でしょう。この手の解説でよくある、主人公の名前はヴィオレッタ《すみれ》なのに、何故『椿姫』なのか?それは日本では原作小説の《いつも椿の花を身に着けていた貴婦人》からオペラの題名をとったため。とか、本来のイタリア語の題名『La traviata』の意味は《道を誤った女》。だとか、ヴィオレッタの職業は《高級娼婦》とどんな解説書を読んでも載っているが、実はフランスでいう《クルティザーヌ》という女性たちは日本人の我々が想像する娼婦というイメージからは程遠い、知性も教養も作法もわきまえた、あたかも貴族のようなポジションの女性たちであった。だとか、このオペラの初演では主人公は肺を患っているはずなのに、立派な体格の女性が務めたことによって会場から失笑が起こり、それが公演の失敗の原因の一つになった。とかいう語りつくされたひとくち物知り講座はさておき、作品の特徴を違った側面から見てみよう。 まずは前奏曲。何声部にもわかれた弦楽器の演奏から始まるこの物悲しい音楽は、主人公の置かれた境遇(病・孤独・虚無)を連想させ、熱く感じるメロディも、あきらめや失望を表わす様に常に下降系のラインを辿る。第1幕の前奏曲と第三幕の前奏曲には共通した数小節のメロディがあるが、第1幕のそれはピンと張りつめたような#系の色彩、第3幕のそれは空気が淀んでいるような♭系のそれを感じる。 第1幕の前奏曲に続いて間髪いれず沸き起こる短い楽句は、シャンパンの栓が跳ぶがごとく、人々の笑いやどよめきが一気に湧き上がるがごとく、主人公ヴィオレッタの主催する豪華なパーティーに聴く者をあっという間に引きずりこむ。このあたりのヴェルディの作劇・作曲技法は絶妙でオペラ指揮者はみな大好きな部分。 有名な「乾杯の歌」が済むと舞台の裏にセッティングされた別の楽団が演奏を始める。これはボールルーム(舞踏会場)から聞こえてくるという設定。この音楽に乗って舞台上にいる合唱団やソリストたちが歌うのだが、現代なら音響設備や映像設備が発達しているから、舞台裏で鳴っている音にオンタイムで歌うということはそれほど難しいことでは無いが、初演された19世紀当時は指揮者がどうやって音楽をまとめていたのかとても知りたい。(ちなみに今回は経費節減のため舞台裏の楽団は居ません、悪しからず。) アルフレードの愛の告白(このメロディが後にとても重要になってくる)が終わって、合唱団が戻ってくると、「ああ、そはかのひとか~花より花へ」という名訳で有名な主人公のアリアが始まる。このときに本来はヴィオレッタの頭の中で聞こえているはずのアルフレードの愛の告白(前述したメロディ)が主人公だけではなく観客の皆さんにも聴こえてくるのだが、これはアルフレードが舞台裏で歌ってくれる。(リハーサル時にはこれをどのあたりで歌えば観客に効果的なのかを探るため、音楽スタッフ達が客席を走り回ることでしょう。)そしてこのアルフレードの舞台裏の歌にはもう一つカラクリが。天国から響くようなアルフレードのこの歌声はハープの演奏に伴われます。実はこのハープ、全曲を通してこの部分でしか使われていません。ですからハープ奏者の方は第1幕のこの自分の出番が終わると寂しく待っているしかないのです。 第3幕幕切れ、それまでの悲しい雰囲気から一転してあのアルフレードの愛の旋律が聞こえてくるとヴィオレッタは言います。「変だわ、痛みがなくなった、私はもういちど生き返るのよ」と、しかしその後激しい音楽の中彼女はこと切れるのです。普段の慣習ではその部分はオーケストラだけが演奏して死んでゆくヴィオレッタにだけスポットが当たるようになりますが、実は彼女の最後を見届けるアンニーナ、ジェルモン、アルフレード、医者には最後の最後まで歌があります。私も演出的、作劇的にはやはりこの部分の歌は無いほうが緊張感があっていいと思いますが、一方でせっかくヴェルディさんが創った音符を歌わないのは大変申し訳ないという気持ちを持ちながらいままで演奏してきました。 今回も慣習に負けてしまうのでしょうか。それは観てのお楽しみに!皆様は歌がある方が良いですか?無い方がよいですか? カフェコンチェルトシリーズVol.1 4月17日(日)牧村邦彦のマイタウンオペラ椿姫へのプロローグにお越しになれば、牧村氏の楽しいお話をもっともっと聞くことができます。 >> 詳しくはこちら |
 |
| >> チケット販売所の店舗地図はこちら |